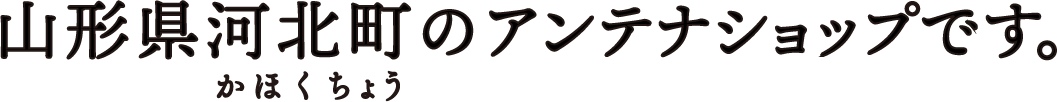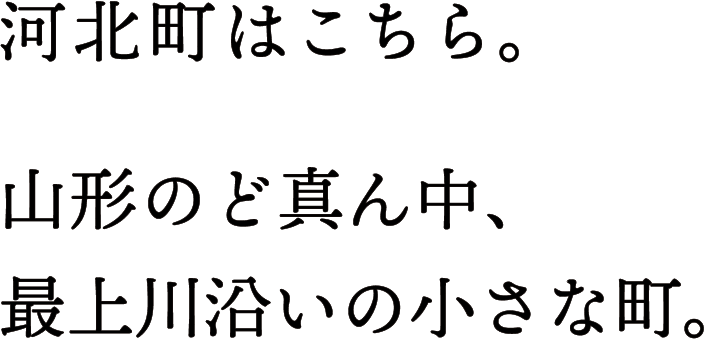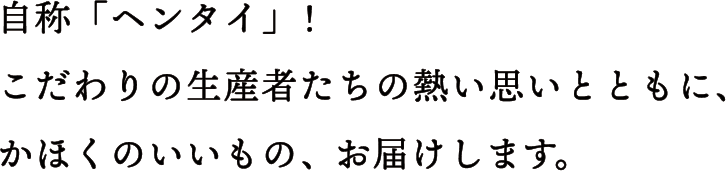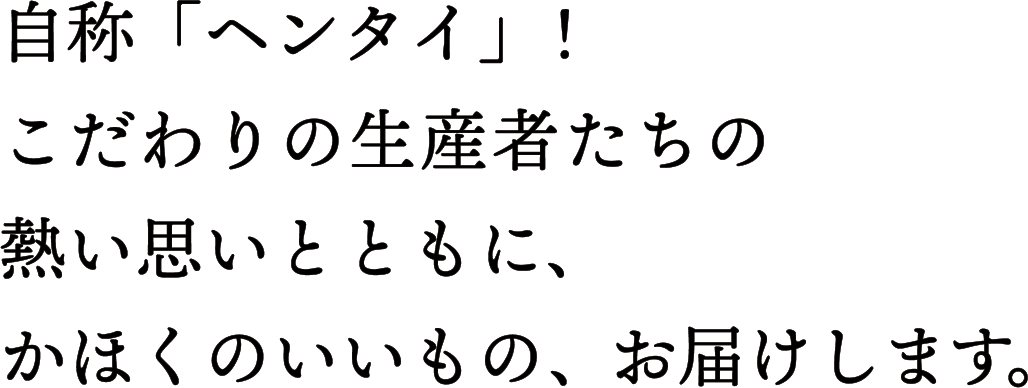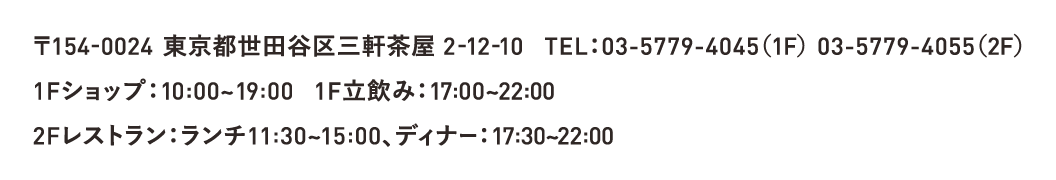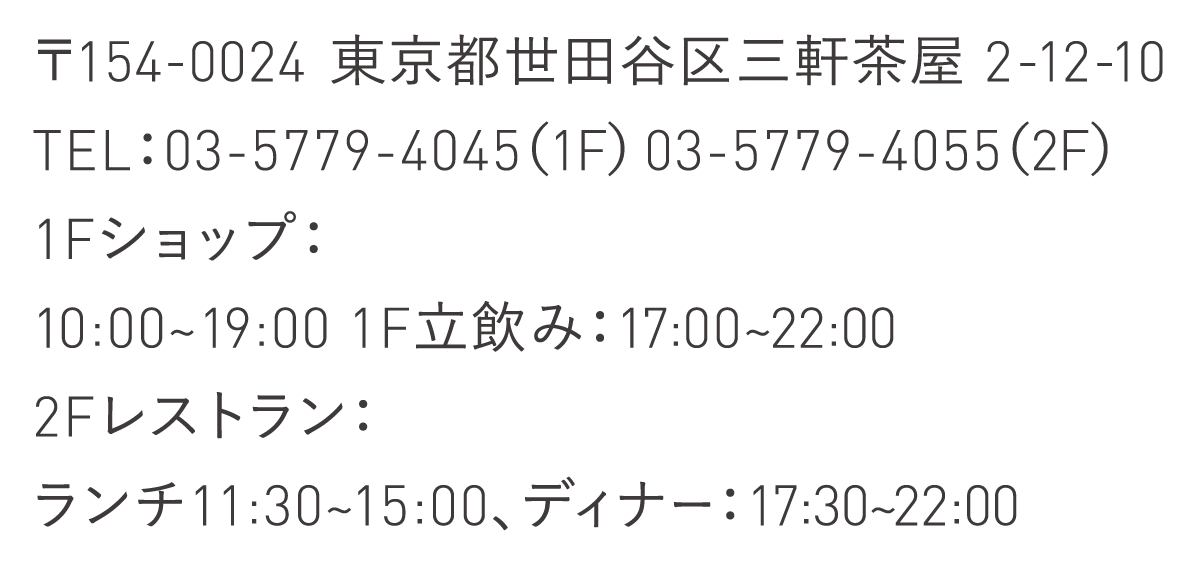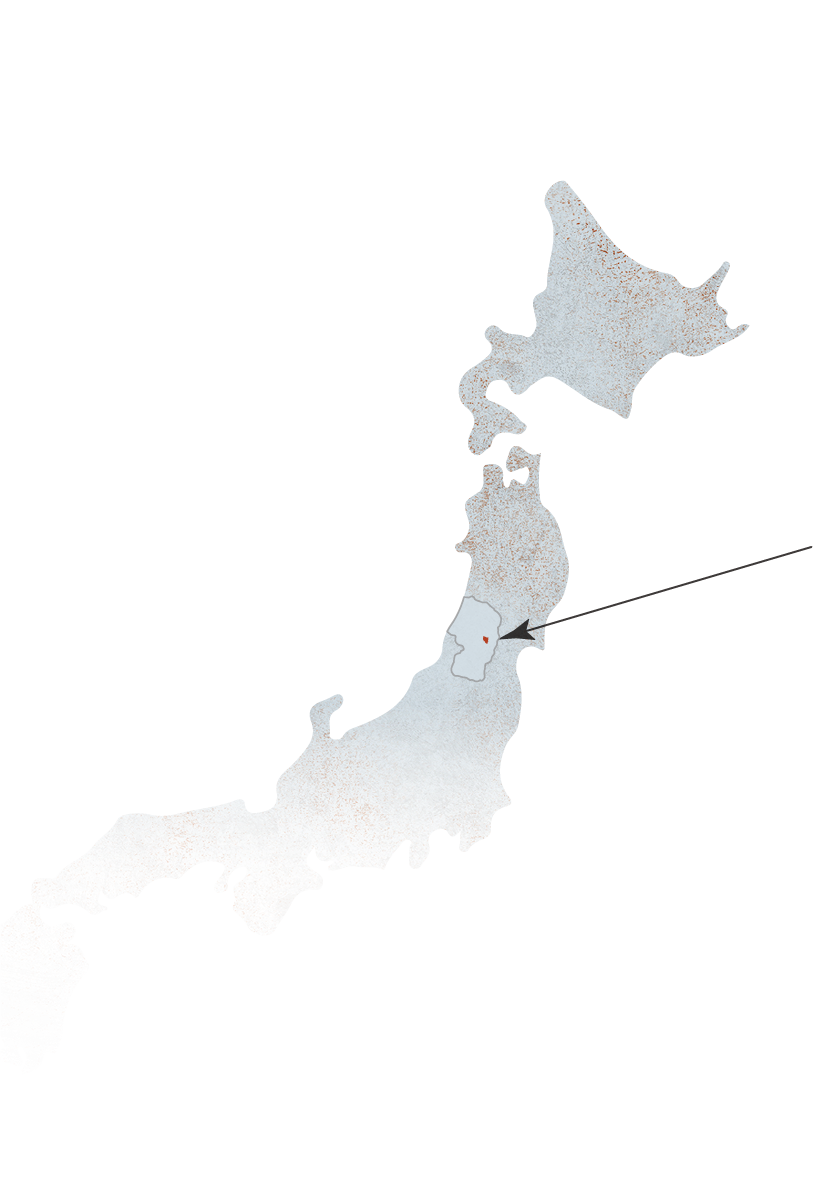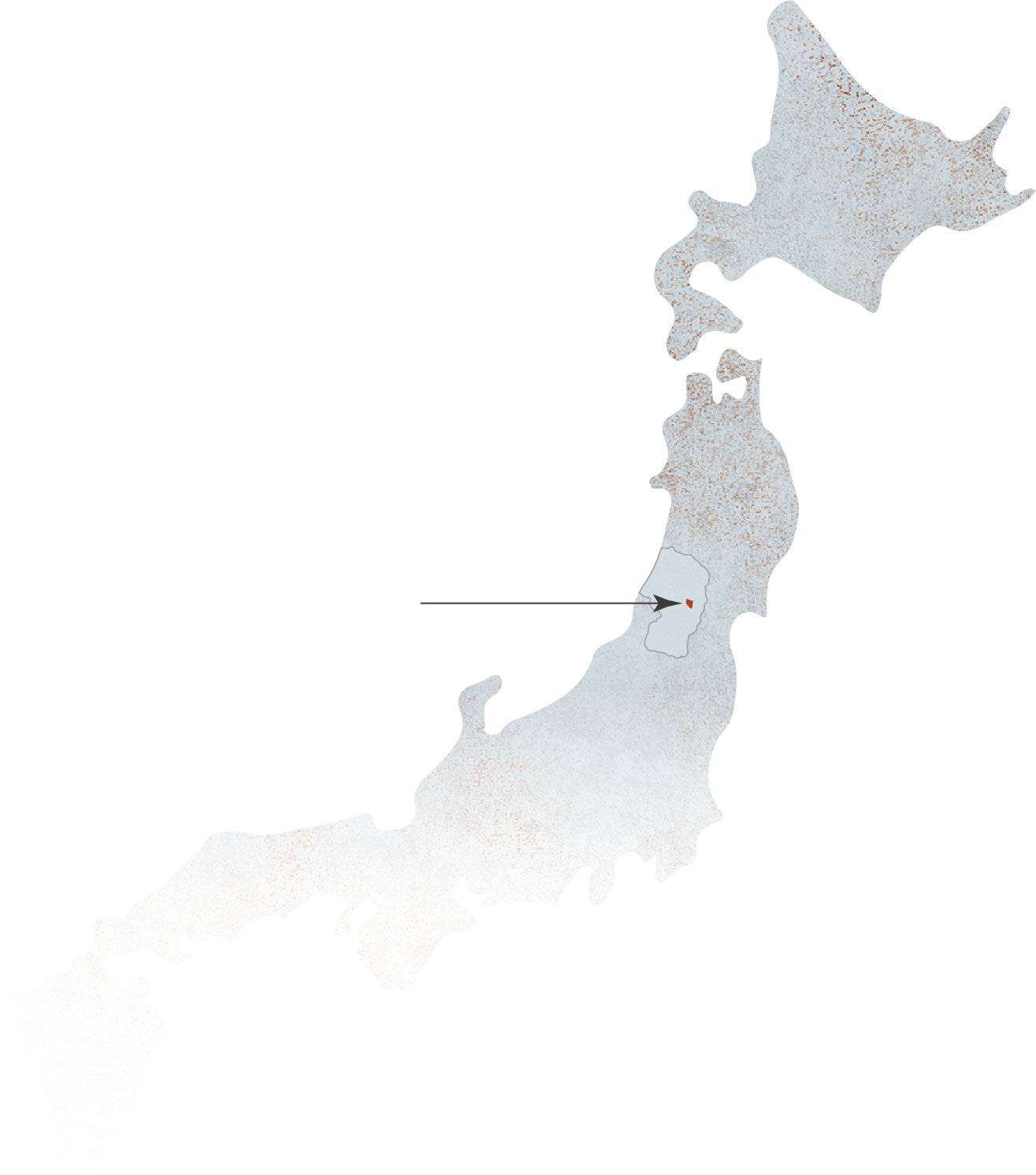「秘伝豆」は、河北町で盛んに栽培されている希少品種の大豆。ふっくら大粒で中まで緑色。「塩茹で」が最も美味しい食べ方だと地元の方が太鼓判を押す理由は、素材そのものの食味がとても強いから。その味の濃さと甘み、香りは、普通の枝豆の何倍もあると評判で、一度食べるとその違いに納得です。東北地方でしか栽培されておらず、秘伝豆を使った商品が関東に出回ることはほとんどありませんが、かほくらし店舗で扱う「秘伝豆豆腐」は、その特有の旨みがしっかりと感じられる逸品。人気も熱く、棚からすぐになくなってしまいます。今回は、そんな「秘伝豆豆腐」を手がける「青柳食品」さんの工場にお邪魔してきました。風通しも日当たりも良く、人も優しく、とても良い空気の流れるものづくりの場。秘伝豆豆腐の他にも、山形らしい大豆製品に出会うことができました。
工場に足を踏み入れた途端、ふわっと鼻を包む大豆の香り。しかし、「匂いします?」と社長の青柳さん。「いつものことでもう鼻が慣れてしまって」と笑います。「青柳食品」は地元で大豆製品を作り続けて三十年以上。「こだわりなんて特にないんだけどよ」と言いつつ、豆腐作りで大変重要な水は、質の良い地元の地下水を使い、年間七百五十俵(一俵=六十キロ)ほど扱う原料の大豆は、常に地元産を使います。
価格高騰がいくら厳しくなっても、地元産を使い続けることだけは変えずに行きたい、と青柳さん。また、大量のストックを回していく工場では収穫したての豆を製品に使えないことが多いのも事実。しかし地元で愛される秘伝豆の香りを少しでも感じて欲しいと、旬の時期には新豆をブレンドしています。
乾燥状態の秘伝豆は、うっすらと綺麗な緑色。水に戻すと二倍ほどに膨れます。「秘伝豆豆腐」はうっすらと緑色で、一般的な絹豆腐よりも少し硬めなのが特徴。作る工程は至ってシンプル。秘伝豆豆腐秘伝豆をすり下ろし、九十八度まで煮てから蒸気で蒸しあげます。そして豆乳とおからに分離させ、粗熱が取れたらニガリを入れ、冷やして完成。このニガリを入れる工程は完全に手作業で行われていました。ニガリの量は豆腐の硬さや水っぽさを左右します。また、天候やさまざまな条件により、固まり具合も異なるのだとか。目でその日の豆乳の状態を確認し、鮮やかな手つきで豆乳をひとすくいし、分量を微妙に調整してからのニガリ投入。粗熱が取れた状態の上澄みをすくって、いわゆる秘伝豆おぼろ豆腐を一口いただいた瞬間、口に広がる青豆の香りとコク。青柳さん曰く、一般の大豆で作った方が滑らかさは出るものの、この香りと食味は秘伝豆特有のもの。冷奴でも十分食べ応えのある一品です。
自然光が明るい「青柳食品」の工場内。窓の外には、河北町らしい田んぼの風景が広がります。黄金色の稲穂が広がる窓際で、手作業で揚げられるやはり黄金色の「三角揚げ」は、山形らしい大判の厚揚げ。揚げる前の白い生地は高野豆腐のような見た目で中身がぎっしり。これを低温と高温と分けて焼くことで、外はカリカリ、中はしっとりふわふわに揚がるのです。煮物にも、お鍋にも最適ですが、焼いて生姜醤油だけでも満足のお味とサイズです。また、山形のソウルフードである玉こんにゃく『たまさぶろう』は『芋煮』には欠かせない食材。弾ける様なプリッとした食感が特徴です。不思議な形の「栄養とうふ」は、固まる前に袋に充填し、その形で固めるという昔ながらの商品。手作業で充填作業をされていました。他にも豆乳や厚揚げなど、昔ながらで毎日のお共に欲しい商品の製造ラインナップが並んでいました。地元の家庭の味を支えてきたことが容易に想像できます。現社長の青柳さんのお母様(写真右)も、現役で工場を手伝います。お母様の、絹豆腐のように真っ白なお肌が印象的でした。