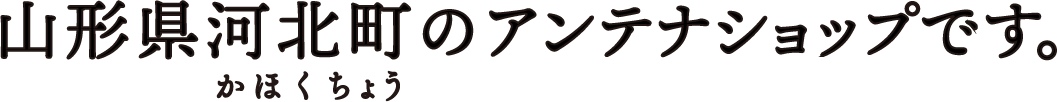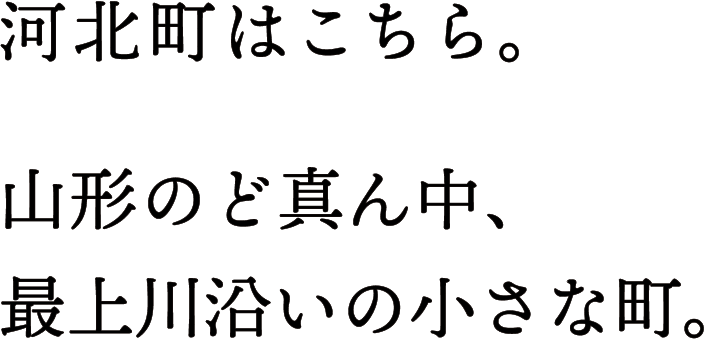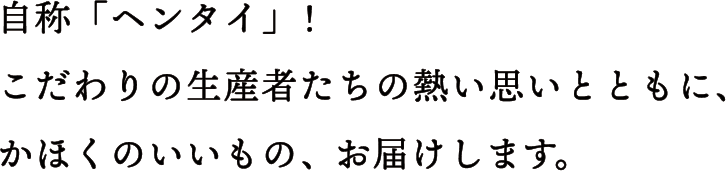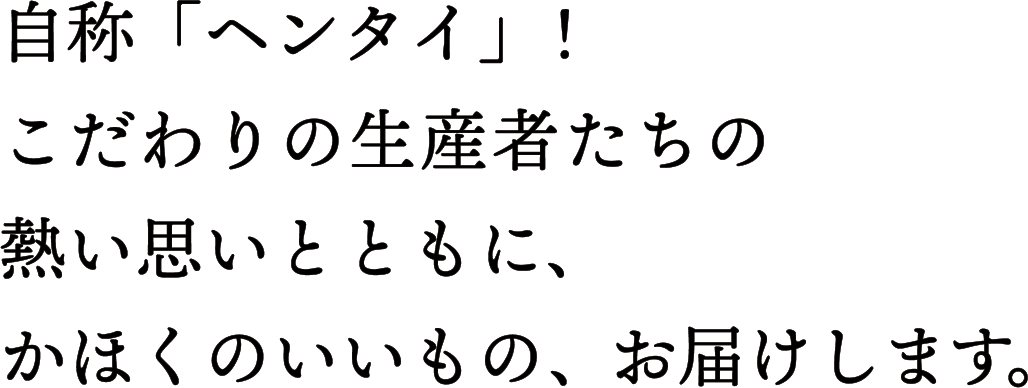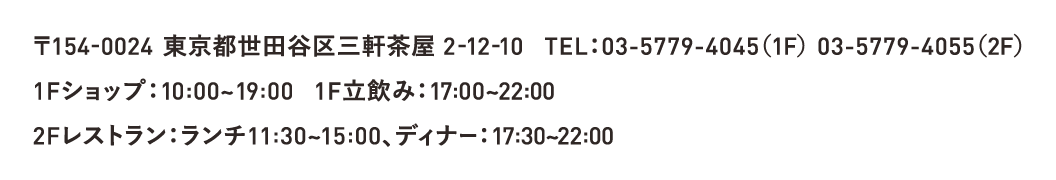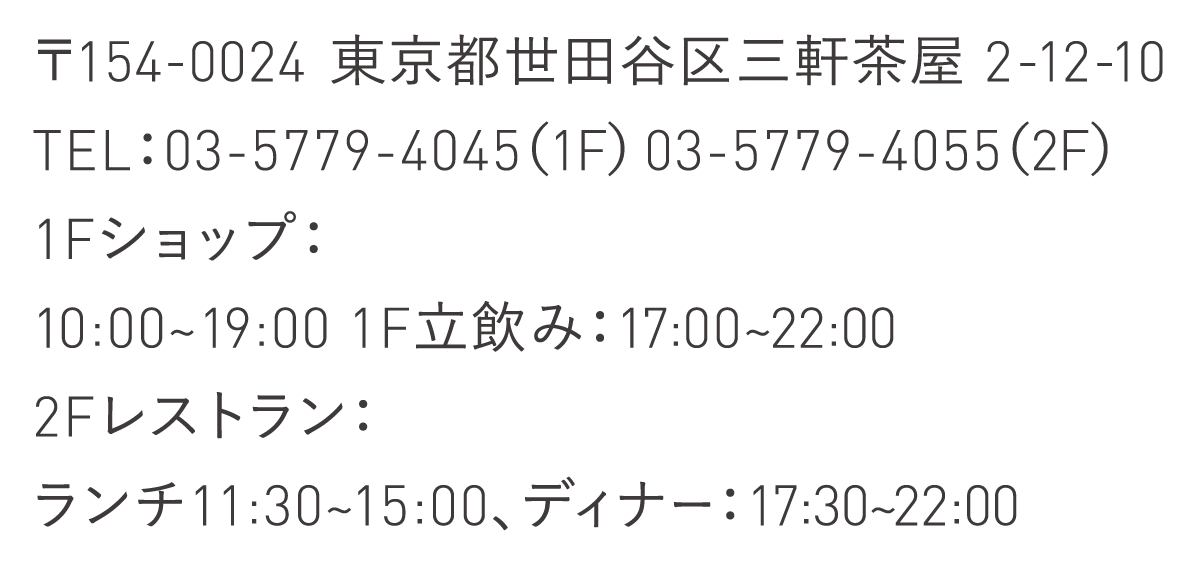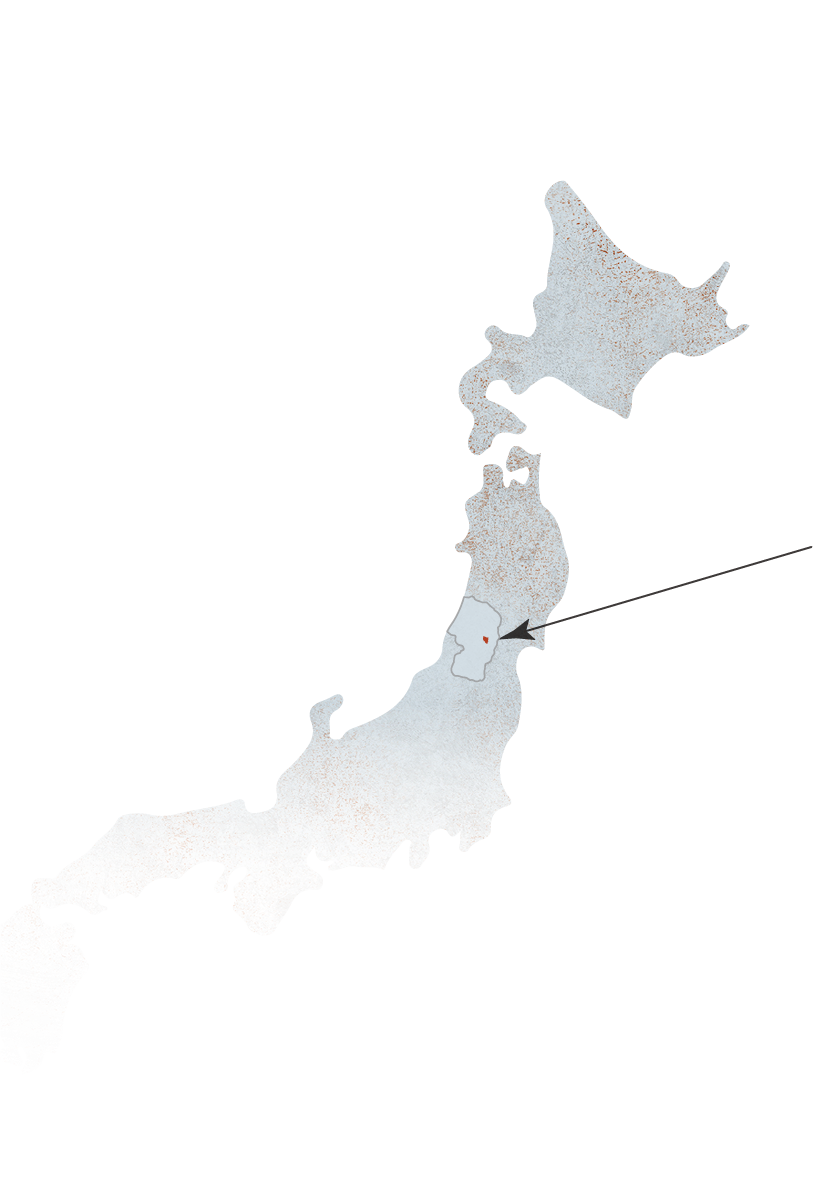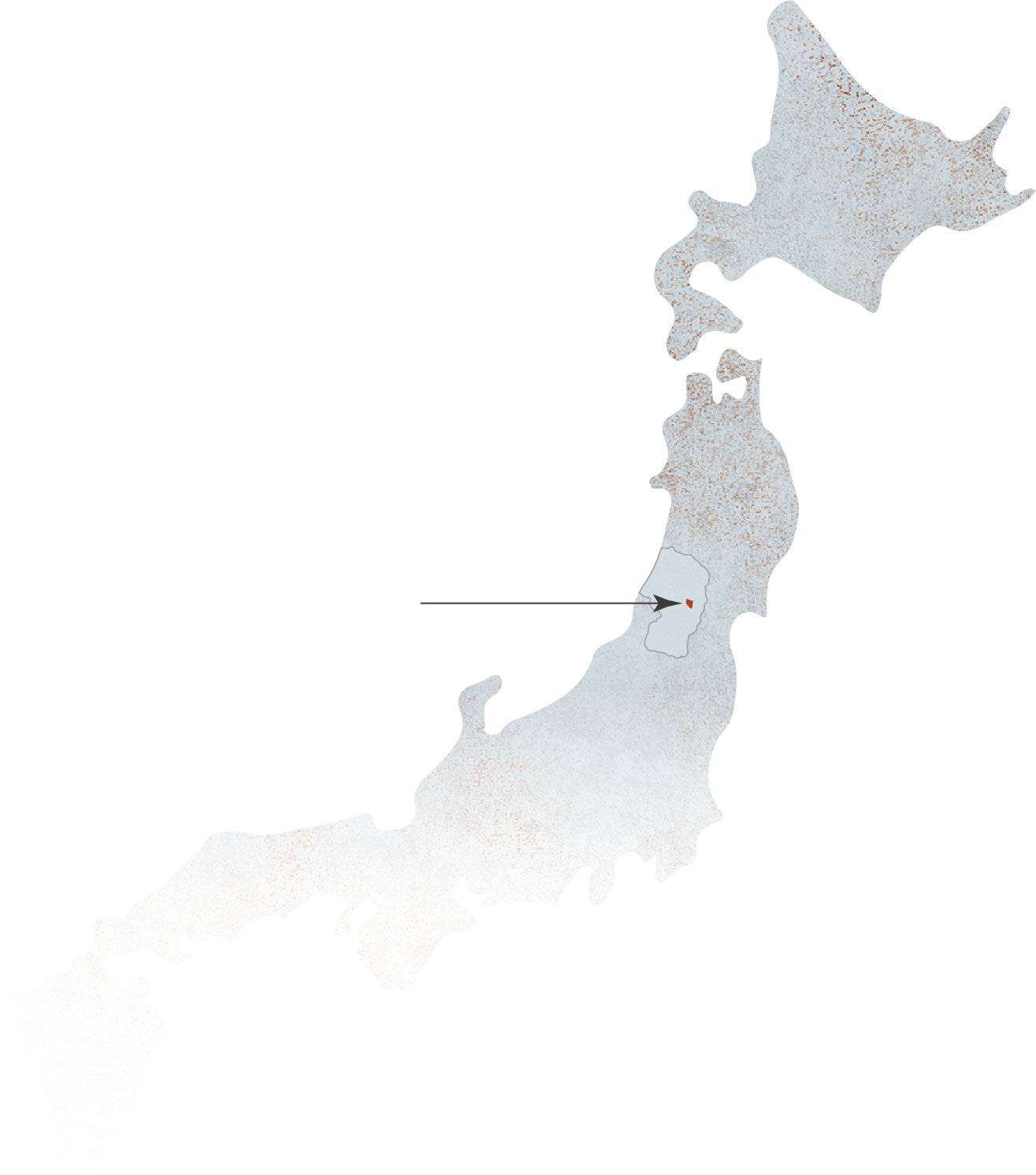兄弟でつくりあげる幻の高級山形牛
「千日和牛」はその名の通り、千日もの手間ひまをかけて大切に育てられる幻の山形牛。年間八十〜百頭ほどしか出荷されません。手がけるのは、兄は「牛バカ」弟は「肉バカ」と河北町内で親しまれる「斉藤畜産」三代目兄弟のお二人。勇輔さんは山形市内の肉牛の競り場で競り人としても活躍してきたほどの目利き。全国各地の牛肉品評会では数えきれないほどのチャンピオンを獲得する実力です。ほとんどが地元消費、県外では特定の得意先にしかおろさないため、関東ではなかなかお目にかかれないスゴイ牛。河北町でどんなふうに育てられているのでしょうか。
「牛に生ききってもらいたい」
一般的には、九百日程度で出荷されるという山形牛。他県ではもっと早く、八百五十日くらいのところもあるそうです。一方「斉藤畜産」では千日かけるのは最低ライン、長いものでは千三百日(=約三年半!)もの期間をかけて世話をする場合もあるのだそう。商売として考えると、もっと早いサイクルでの出荷した方が効率的かもしれませんが、そのこだわりの理由は何なのか尋ねると、勇輔さんの答えは至ってシンプル。しかし本質的なことに気づかされるものでした。「うちは昔から時間をかけて肥育をする農家でしたから、昔ながらのやり方をずっとやっているという感覚なんですよ。」
牛はもともと日本人にとってとても家族的な生き物でした。田んぼや畑を耕す労力として家族で一頭飼い、仕事を終えた牛を最終的にお肉にして出荷するのが一般的だった昔。肥育が職業として定着し、農業と分離した現在、肥育において回転率が重視されるようになりました。「でもそれは、人の都合でしかないですよね。」と勇輔さん。その牛がまだ餌をたくさん食べられるし、もっと良くなる余力がある中で出荷を決めるのは、人間本意なのではないか。霜降りが入ればすぐに出荷するのではなく、霜降りではない部位も、一頭の牛をまるごと美味しく食べられるまで飼いたい。例えそのために百日以上手間がかかっても。「牛の命をもらうというのが仕事な以上、人も牛も納得いくまで」そんなシンプルが思いが、最高の肉質を生み出す技術の根幹にあるようです。
牛任せで肉を仕上げる
昔ながらの牛との向き合い方で、一頭一頭丁寧に手をかけること。そして、代々守ってきた技術の蓄積。その結果生まれる「千日和牛」の定評は、口に入れた瞬間に溶け出す脂の融点の低さと甘みの素晴らしさ。脂の品質には、牛の血統と餌と飼い方全てが作用するため、牛を選ぶ技術も非常に重要です。
血統を厳選するのはもちろん、仔牛の姿で牛の個性や体質を吟味し、角や骨格、体全体の丸みなどでとれる肉の量や質を想定し、飼い方が合いそうな牛を選びます。餌は、斉藤家代々伝わる配合。牛が一生食べる稲藁は必ず河北町産の、「まきの農園」さんのものを混ぜるのがこだわり。牛へのストレスを極力無くすため、一頭一部屋、餌は一日に六〜七キロまで。その量の中で、牛が仕上がるのを待つという、ある種「牛任せ」のスタイル。出荷のタイミングは、日々表情や目を見て、牛を触り、餌の食べ具合、角や毛つや、牛の目など様々なところで判断します。子でも代々伝わる肌感覚があるそう。信念をもってゆっくりのびのびと育て、肉を少しずつ大きくすることで、脂のキメも細かくなり、肉質も全体的になめらかに仕上がります。健康的な脂身の持つ甘みは格別です。
牛がお肉になってからは、熟成のプロである弟の大知さんの腕に全て任せます。直営の焼肉店「正福」は、いつも町内外のお客さんで賑わい、予約しないとなかなか入れません。「時々母が振る舞う牛すじの煮込みも絶品なので、ぜひ河北町に来て食べて欲しいです」。(つづく)
『牛にかける千日の想い その二』は、熟成のプロ、弟・大知さんのご紹介です。
※斉藤畜産HPはこちら